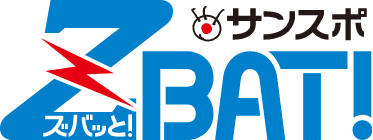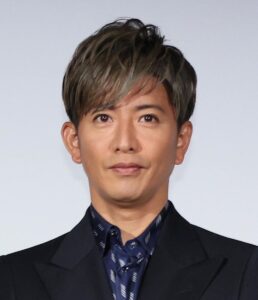そもそも幸運の日とは?
声優の細谷佳正さん(43)が10日、公式Xで結婚を発表しました。
細谷さんは、占いやスピリチュアルにも造詣が深く、結婚を発表した当日は「一粒万倍日」(いちりゅうまんばいにち)という〝幸運の日〟でした。
幸運の日と言えば、古くから日本人に馴染みがあるのは六曜の「大安」の日でしょう。結婚式を挙げる定番の日でもありますが、ここ数年それに続くようにして、数々の幸運の日がSNSで取り上げられています。
そもそもの話、幸運の日とは、どんな日なのでしょうか?
筆頭格が「一粒万倍日」
幸運の日の中でも〝筆頭格〟と言われているのが「一粒万倍日」です。
国立国会図書館のウェブサイト内「暦の中のことば」(https://www.ndl.go.jp/koyomi/chapter3/index.html)によると「ひと粒のモミが万倍にも実る稲穂になるというめでたい日のことで、万事を始めるによい日とされる。とくに、仕事始め、開店、種まき、出金などは吉だが、増える意味があるため、借金、借り物は凶とされている」とあり、お米を主食とする日本らしい「稲穂」が由来となっている幸運の日です。
一粒万倍日と並んで、聞くことが多いのは「天赦日」(てんしゃにち)でしょうか。こちらは暦の中のことばで「百神が天に会合し、天が万物を許す日であり、万事にわたって吉とする。四季により日が変わる」と記載されています。
この2つの幸運の日とあわせて有名なのは、暦上に記載される位置から名づけられ、十二直(じゅうにちょく)とも呼ばれている「寅の日」(とらのひ)でしょうか。
こちらは「十二直の意味の解釈は時代によって少しづつ異なっています。現在ではほとんど使われることはなくなりましたが、建築や引越しの吉凶を見るために使われることもあります」と記されています。ただ、時代とともに解釈が変わっていることもあり、現在言われる「金運に良い」という根拠は見つかっていないようです。
上記の通り、古くから日本に伝わるものもあれば、徐々に変化し使われ始めた頃からは意味が変化している言葉等、様々な由来があることがわかりました。
これをきっかけに、改めて日本古来からの幸運の日を調べてみたり、自分自身の幸運の日を考えてみるのも良いかもしれませんね。