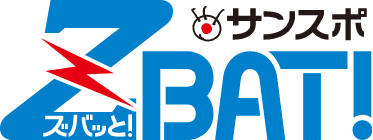無線型が主流に
通勤中の強い味方、イヤホン。
最近では、有線イヤホンから、無線型の「ワイヤレスイヤホン」が主流となりつつあります。とりわけAppleが2016年末に発売した「AirPods」以降、イヤホンと言えば無線というのが一般的になりつつあるようです。
無線イヤホンは、有線のようにスマホと両耳をケーブルで直接繋ぐことがないため、かさばらず、移動中に線がからまることもありません。このため、移動時の利便性が格段に向上しました。
さらに、2019年にAppleが「AirPods Pro」を発売。これは「AirPods」と異なり、両耳を密閉する設計となっており、ノイズキャンセリング機能が搭載されています。
ノイズキャンセリング機能は、耳栓のように物理的に耳を塞ぐ方法や、デジタル的に音を処理する方法など、さまざまな技術があります。これにより、騒音が大きい場所や周囲の音を気にせず、仕事や勉強に集中できるようになりました。
長時間使うリスクも
ただし、便利なイヤホンを長時間使用することによるリスクも増えています。最近では、10代から30代の聴力低下が進んでおり、「イヤホン難聴」に悩まされる人が増えていることをご存じでしょうか。
世界保健機関(WHO)によると、イヤホンによる難聴のリスクがある人は、世界で約11億人にのぼるとも言われています。
では、なぜイヤホン難聴が起きるのでしょうか。
イヤホンで音を聞くと、その音は耳の中に入ります。鼓膜を通り、かたつむりのような形をした器官である蝸牛にある有毛細胞によって振動が電気信号に変換され、脳に伝わります。この有毛細胞は、一度傷ついてしまうと再生しないため、聴力が低下した場合には回復しにくいのです。
難聴を防ぐ方法は?
それでは、イヤホン難聴を防ぐためにはどうすれば良いのでしょうか。
耳も人間の体の一部であるため、適度に休ませてあげることが大切です。例えば、1時間に10分間、イヤホンを外して耳を休ませることが推奨されています。また、1日のうちでイヤホンを使わない時間帯を決めると、習慣として続けやすくなります。
ネットでもこの問題についての反応があります。
例えば、「イヤホンを使う機会が多いため、気を付けたい」という声や、「会社の若い社員がずっとイヤホンをつけていて心配」という意見も見受けられます。一方で、「イヤホンが原因ではなく、大音量で聞くことが問題だ」という指摘もあります。
通勤時や移動時に便利なイヤホン。私たちの生活に欠かせないアイテムですが、その使い方には十分注意し、耳を大切にしながらうまく付き合っていきたいものです。